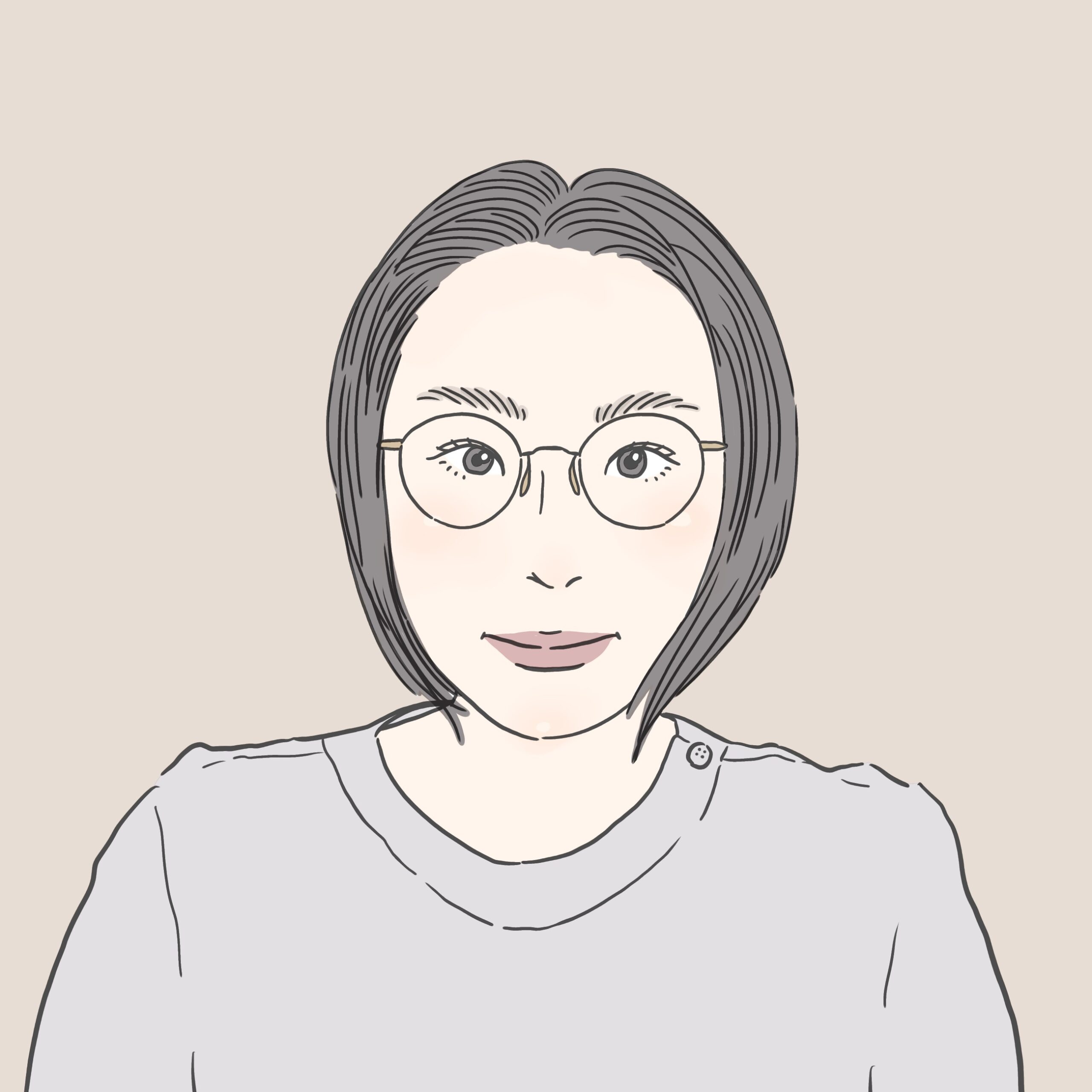お友達のきりさんに会うため、富山県魚津市に行った。いつ知ったのか定かではないのだけれど、魚津市には現存する日本最古の水族館と埋没林博物館があるということを知って、ずっと気になっていた。2023年のゴールデンウィークにも富山を訪れたのだけど、その時は飛騨高山で一泊、富山市内で一泊という旅程の関係で、魚津水族館は時間に無理があって行けなかった。ふと、今年の頭に「魚津水族館に行こう」と思いたち、7月の連休がよさそうと考えてホテルを予約し、その勢いできりさんに連絡を取った。魚津はきりさんの町。そうしたら、魚津をご案内してくださり、晩ごはんもご一緒することになった。わたしとしてはお茶ができたらよいなという気持ちだったので、とても嬉しい。
朝、特急サンダーバードに乗って大阪から敦賀へ向かう。快適な温度と適度な揺れで眠ってしまう。敦賀駅で降りる人はほぼ全て北陸新幹線に乗り換えるわけで、三連休初日の午前中の駅構内は大変混雑していた。無事に北陸新幹線のつるぎに乗り、終点の富山駅で一旦改札を出る。お迎えの人が何組も待っていて、短い帰省の人もきっとたくさんいるのだ。駅構内でお昼ごはん。それから、あいの風とやま鉄道に乗り込み、いざ魚津へ。
魚津駅の改札口できりさんが待っていてくださった。お会いするのは6年ぶりだけれど、すぐにわかるものなんだな。6年分歳を重ねたけれど、お互い元気だから今日会えるのだ。
まずは魚津水族館へ向かう。小さめの地元に密着した水族館で、ペンギンプールは無料で見られる。暑いから外にいるペンギンは少ない。中に入ると、富山湾を中心に富山の魚がたくさん展示されている。淡水魚も海水魚も食べられる魚が多い。というか、食べてみたら美味しいとか調理が大変とか、寿司の解説とかが貼ってある。ゲンゲという魚は「幻の魚と書いてゲンゲです。これも食べます」ときりさんが言うので、幻の魚なのに食べちゃうの?!とびっくりした。日本最古というだけあって、大水槽のところにあるトンネルも日本初らしい。子どももたくさんいて、地元の人たちに愛されている場所だ。「お魚ショーが始まります」というアナウンスがあって、魚が何をするのだろうと思っていたら、イシダイが紐を引っ張って文字が書いてあるプレートを見せたり、ウマヅラハギが輪くぐりをしたりして、魚を侮っていた。
続いて、水族館の向かいにあるミラージュランドへ。ここにある観覧車は日本海側最大だそう。確かにとても見晴らしがよい。山には雪が少し残っていて、日本海はいかにも「夏!」というようなきらめき。プールも賑わっている。
その次は、埋没林博物館。巨大な木の根っこの化石になるのかしら。乾燥展示室と水中展示室があって、乾燥展示室は間近で大きさを体感できる。水中展示室はすごく不思議なものを見た気持ちになる。木の根っこが水の中にそのままの形で存在している。蜃気楼についても展示があって、予報と観測記録が掲示されていた。今年はAランクやBランクがなくて、不作だなあと思った。きりさんによると「蜃気楼は『出たよ!』と言われて見に行っても消えてしまっている」そう。生き物や地球の不思議。KININAL(キニナル)という併設のカフェで休憩する。フルーツそのままの見た目のケーキがあって美味しそうだったけれど、晩ごはんが食べられなくなりそうなので、丸ごとりんごのジュースにする。中身をくり抜いたりんごが器になっていて、ジュースだけでなく、食べてみた蓋の部分も美味しい。「魚津はりんごの産地なんですよ」ときりさん。
そのあと、山のほうにある東山円筒分水槽へ。ここへ向かう途中にりんご園が見えた。海から近いのに?と思ったら、魚津は高低差が大きい町で、海からすぐ山になるとのこと。東山円筒分水槽は3つの用水路に水を均等に配分する装置で、水が勢いよく落ちる様子と、周りの田んぼ、奥に海が見える景色はとても綺麗だった。祖父母の暮らしていた町がちょうどこんな、住宅地が終わって田畑が多くなる山の入り口といった場所だったので、懐かしい気持ちになる。
そして、晩ごはん。きりさんがお魚料理のお店を予約してくださっていた。大阪ではなかなか美味しい魚が食べられない。お刺身盛り合わせの鮮度が全然違う。バイ貝は初めて食べた。貝でこんなシャキシャキとした歯応えのものがあるなんて、思ってもみなかった。天ぷらも盛りだくさん。
最初にきりさんとお会いしたのは文学フリマ大阪だった。わたしが文フリというイベントを知って初めて出かけて、きりさんの小説を「文章がよいなあ」と思って手に取ったのがきっかけ。海の描写がとても印象的だった。わたしが感想をTwitterに書いて、それをきりさんが見つけ、相互フォローになった。そこから10年経った。お互いが出るイベントごとにお会いしていて、わたしは彼女の小説を買っては読み、今でも手元に置いている。きりさんがイベントに出るのをやめられてからは、お会いする機会がなかったのだけれど、SNSではずっと繋がりを保っていた。お互いいろいろな変化がある中で、関係が続いているのはすごくありがたいことだ。
10年目にして初めてこれだけ長い時間をご一緒し、KININALでお茶をしながら、晩ごはんを食べながら、ゆっくりお話しした。初めは少しぎこちなさもあったけれど、小説と詩でジャンルは違っても創作を続けているから、書くこと、読んでもらうこと、本にすること、続けること、小説や詩を読むことなど話すことはたくさんあった。「わたしが書かなくても誰も困らないけれど、書きたいから書くしかないし、書いたからには読んでもらいたい」とか「自分でやり切ったと思えるまでは、書き続けるしかない」とか。どういう結果が出るとか出ないとかではなく、自分が納得するまではやめられるものではないのだと思う。わたしはきりさんの文章が好きだから、また創作小説の本を作ってくれたら嬉しいなあと思った。
ホテルに戻ってから、きりさんがイベントに出られていた頃にお話しする機会を持てたらよかったな、という気持ちになったのだけれど、その頃のわたしは創作周りの人間関係で嫌な目にあったり、自分は小説を書く人ではないという謎の引け目があったりして、お声がけする勇気が出なかった。でも、遅すぎるということはなくて、ここから関係を重ねていったらよいのだ。毎年とは言わないけれど、できることなら2〜3年に1回くらいお会いして、長く繋がりを保っていきたいなあと思う。いつか創作をやり切ったと思う日が来ても、変わらずに。
翌朝、魚津港のほうまで散歩してもいいかなと思っていたけれど、暑くて往復歩くのは危険そうだったのでやめて、9時台の電車で富山へ向かう。帰りの新幹線まで6時間くらいあるから、富山市ガラス美術館と、富岩運河環水公園かお城を見に行こうかなと思う。富山駅でなんとかコインロッカーに空きを見つけて荷物を預ける。一旦、サンマルクカフェに入って前日の日記をノートに書いて、小説を少し読んだ。
ガラス美術館へ。駅から外へ出ると日差しが眩しくて暑い。これは、富岩運河環水公園には行かないほうがよさそう。路面電車で総曲輪エリアに着く。ガラス美術館の展示は見応えがあって、1時間以上かけて見た。ガラスというと儚さや透明感といったイメージだけれど、ここのガラスは力強さや躍動感、生命力がある。見終わったら12:30をとっくに過ぎていて、ミュージアムショップを見る前に、斜め向かいのフェリオ総曲輪でお昼ごはんを食べる。さすが三連休、お店は混んでいて並んでから食べ終わるまで1時間以上かかった。地下の銘店街でお土産を買う。ガラス美術館に戻って、ミュージアムショップで箸置きを買った。キラキラしている。前に来たときも買ったのだけれど、洗っているときに手を滑らせてシンクに落として割ってしまった。飾ろうかな。どこかへ行くにはもう時間がなく、併設のカフェでクリームソーダを飲む。グラスは多分富山ガラスで、模様が美しい。
帰りの新幹線は、行きと違って空いていた。大阪に着いたあと、ルクアで晩ごはんを食べ、コーヒーを飲んで一息ついてから帰宅した。
今まで旅行というと見たいものがある場所へ行っていたけれど、友達に会いに行く旅行もよいものだと思った。何も近くにいて頻繁に会うだけが友達ではなくて、遠くてたまにしか会えなくても普段はSNSなどでやりとりして繋がって、ふとしたときに会いに行ったらよいのだ。会いに来てくれたら、もちろん歓迎する。
やりたいことをやり、会いたい人に会うためにも、生活と詩と遊びのバランスを整えて、日常生活をしっかり送ろう。目の前の楽しさだけでなく、未来の楽しさも視野に入れて。